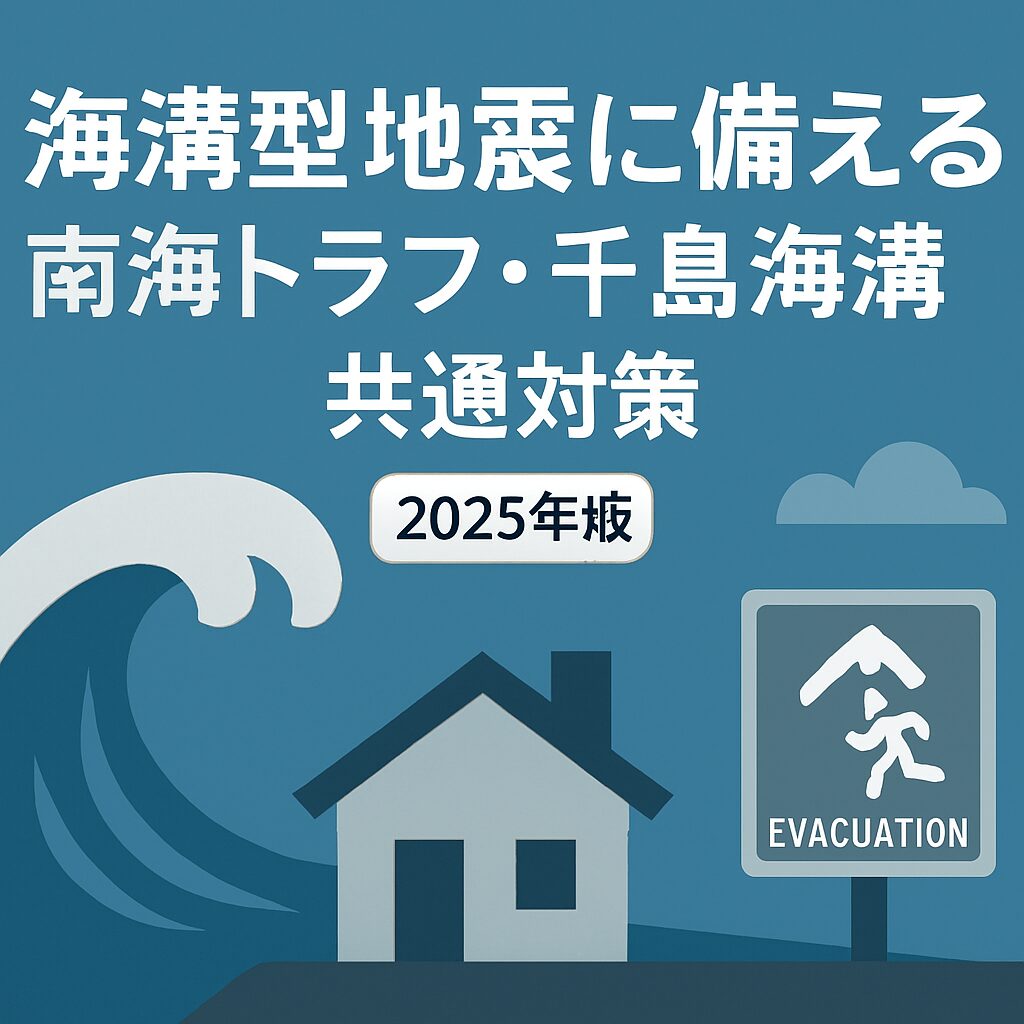目次
はじめに|停電は「電気が止まる」だけじゃない
地震による停電は、照明だけでなく、水道・ガス・通信など、生活の根幹を揺るがします。 特に南海トラフ地震や千島海溝型地震のような広域災害では、支援物資が届くまでに最低3日、場合によっては1週間以上かかることも。
「水はあった。でも冷たいご飯ばかりで、食べる気力がなくなった」──そんな声が、実際の避難所から届いています。 このページでは、停電時に必要な「水・食料」の具体的な量と、実際に役立った備え方を紹介します。
水の備蓄|量だけでなく“飲みやすさ”も考える
推奨量
-
飲料水:1人1日3L × 3日分 = 9L/人
-
例:4人家族なら36L(2Lペットボトル18本)
生活用水
-
手洗い・トイレなどに10〜20L程度あると安心
-
備え方:お風呂に水を張っておく/ポリタンクに水道水を保存
実際の声
-
「冷蔵庫の水は冷たすぎて子どもが嫌がった。常温保存が大事」
-
「2Lペットは重くて持ち運びにくかった。500mlも混ぜておくべきだった」
食料の選び方|“食べられる”と“食べたい”は違う
1人3日分の目安
| 食料品 | 数量の目安 |
|---|---|
| アルファ米 | 3〜6食分 |
| 缶詰(魚・肉・野菜) | 3〜5個 |
| レトルト食品(カレー・おかゆなど) | 3〜5個 |
| 乾パン・クラッカー | 1袋 |
| チョコ・クッキー | 各1個 |
| 野菜ジュース・果物缶 | 3本/個 |
実際の声
-
「缶詰は便利だけど、プルタブ式じゃないと開けられなかった」
-
「甘いものばかりで気持ちが沈んだ。塩気のあるものが欲しかった」
-
「避難所でふりかけを分け合った。味が“日常”を思い出させてくれた」
特別な配慮が必要な場合
-
乳幼児:液体ミルク15回分/離乳食9食分
-
高齢者:噛みやすいレトルト・栄養補助食品を9食分
-
アレルギー対応:除去食・専用ミルクなどを余分に確保
調理と食器|火と器が“食事”に変える
-
カセットコンロ+ボンベ(最低3本)
-
ラップ・紙皿・割り箸(洗い物不要)
-
ウェットティッシュ・ゴミ袋(衛生管理)
実際の声
-
「ラップを敷いて皿を使った。水がなくても清潔に保てた」
-
「ボンベが足りなくて、途中から冷たい食事に戻った。3本じゃ足りないかも」
食べるタイミングと心理|温かいものが心を支える
-
朝:糖分・水分補給(ゼリー・パン)
-
昼:主食+たんぱく質(缶詰・ご飯)
-
夜:温かいもの・塩分(スープ・味噌汁)
実際の声
-
「冷たいご飯ばかりで、温かい味噌汁に涙が出た」
-
「甘いものばかりで気持ちが沈んだ。塩気のあるものが欲しかった」
保管と点検
-
保管場所:すぐに持ち出せる場所+分散保管(玄関・車・寝室など)
-
定期点検:賞味期限の確認/年に2回は見直し
-
ローリングストック:日常で使いながら、非常時にも使える備蓄法
👉 ローリングストックの詳しい方法はで紹介しています。
まとめ|備蓄は“量”より“使えるかどうか”
停電は「電気が止まる」だけではなく、生活の連鎖が止まること。 だからこそ、数字だけでなく、実際に使えるかどうかを基準に備えることが、未来の安心につながります。
「食べられる」ではなく「食べたい」ものを。 「持っている」ではなく「使える」ものを。 それが、災害時に本当に役立つ備えです。