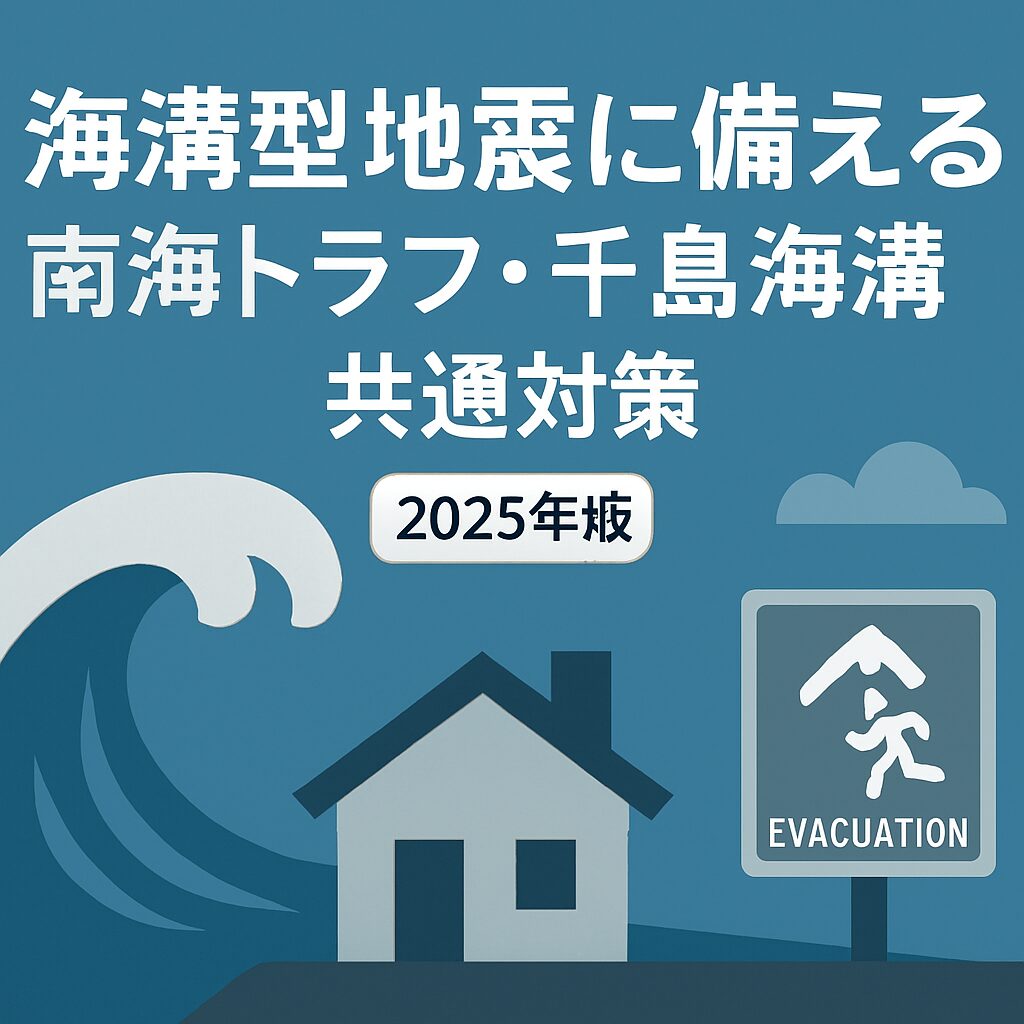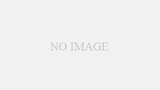目次
はじめに
地震が起きたとき、私たちはまず「揺れ」に意識を向けます。 しかし本当に怖いのは、その後に起こる「二次被害」。火災、津波、停電、感染症──これらは事前の備えで予防できるものも多くあります。 この記事では、地震後に起こりうる二次災害と、それぞれに対する具体的な予防策を整理します。
二次災害とは?
地震による直接的な被害(建物の倒壊・地割れなど)は「一次災害」。 その影響で連鎖的に発生する被害が「二次災害」です。代表的なものには以下があります:
- 火災(通電火災・ガス漏れ)
- 津波
- 土砂崩れ・液状化
- ライフラインの断絶(電気・水道・ガス・通信)
- 感染症・エコノミークラス症候群
- 余震による建物倒壊
火災を防ぐための対策
通電火災とは
停電後に電気が復旧した際、傷んだ配線や倒れた家電に電流が流れて発火する現象です。特に電気ストーブやヒーターなどの暖房器具は危険性が高く、冬季の北海道では注意が必要です。
予防方法:
- 避難時にブレーカーを落とす
- 家電の電源を切る
- 家具・家電を固定して配線損傷を防ぐ
ガス漏れによる火災
地震の揺れでガス管が損傷し、漏れたガスに引火することで火災が発生する可能性があります。ガスメーターの遮断機能は使用中のみ作動するため、未使用時の漏れには注意が必要です。
予防方法:
- 揺れが収まったらガスの元栓を閉める
- ガスメーターの遮断表示を確認する
- ガス機器周辺の安全を確保する
家具・家電の固定
倒れた家電からの出火や、破損した配線による火災を防ぐために、家具や家電の固定は重要です。
予防方法:
- 家具・家電を壁に固定する
- 耐震ラッチを設置して扉の飛び出しを防ぐ
- 寝室には倒れやすい家具を置かない
初期消火の備え
万が一火災が発生した場合、初期段階での消火が命を守る鍵になります。
予防方法:
- 消火器をすぐ手に取れる場所に設置
- 使用方法を家族で共有しておく
- 定期的に消火器の有効期限を確認する
津波・土砂災害への備え
津波・土砂災害とは
地震によって海底や地盤が変動し、津波や土砂崩れが発生することがあります。特に海沿いや傾斜地に住む人は注意が必要です。
予防方法:
- ハザードマップで自宅周辺のリスクを確認
- 高台・避難タワー・徒歩ルートを事前に把握
- 家族で避難訓練を実施しておく
ライフライン断絶への備え
ライフライン断絶とは
地震によって電気・水道・ガス・通信などのインフラが止まり、生活が困難になる状態です。
予防方法:
- 水・食料を最低3日分、理想は1週間分備蓄(1人あたり水9L)
- モバイルバッテリー・ラジオで情報収集と連絡手段を確保
- 簡易トイレ・衛生用品で断水時の衛生環境を守る
感染症・健康被害の予防
避難生活による健康リスク
避難所や車中泊では、衛生環境の悪化や運動不足による健康被害が起こりやすくなります。
予防方法:
- マスク・消毒・ウェットティッシュを備蓄
- 避難所では距離を確保し、定期的に換気
- 車中泊では水分補給と足の運動でエコノミークラス症候群を予防
余震による倒壊を防ぐ
余震の危険性
本震のあとにも強い余震が続くことがあり、損傷した建物が倒壊するリスクがあります。
予防方法:
- 家具の配置を工夫し、寝室には倒れやすいものを置かない
- 建物の耐震診断・補強を検討する
- 避難経路を確保するため、ドアや窓を開けておく
まとめ
地震の揺れが収まったあとこそ、最大の危機が訪れることがあります。 だからこそ、今できる備えが未来の命を守る。 Yuki Baseでは、こうした情報を整理し、読者が「行動に移せる形」で共有していきます。